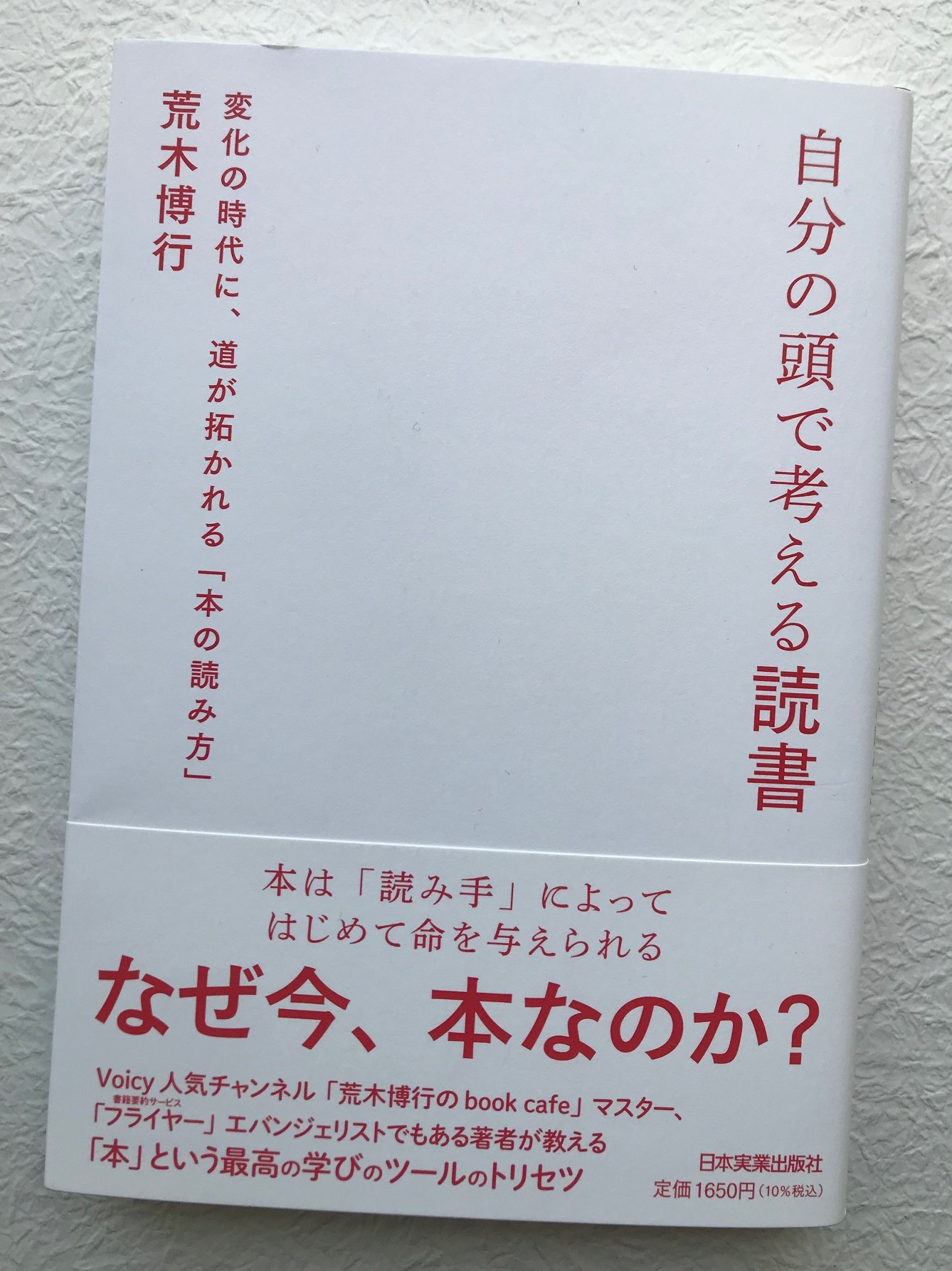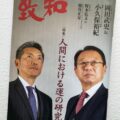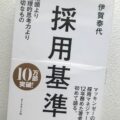本とどう付き合っていくのか?この本は「効果的な読書をするための書」とか「これが読書の全体像だ!」などいうのではなく、むしろ、他人の頭で導き出した答えに対して、自分の頭でも考えることが重要だと訴えています。著者の話を無条件に呑み込むのではなく、何らかな「問い」を持つことで、私たちの頭を駆動させるのです。本を読んだ読者の考えと、著者の考えがひとつになって新たに完成するのです。
自分の頭で考える読書 変化の時代に、道が拓かれる「本の読み方」 [ 荒木 博行 ]
何かを教えるときに、全体像を見せてはいけない
教育のパラドクスとは、教える側がわかりやすく教えれ教えるほど、受けては考えなくなる、という矛盾です。手取り足取り丁寧に示せば、受けては無批判でそのナレッジを受け止めてします。その結果出来上がるのは「教える人の劣化コピー」なのです。
読者の考える力を借りる
コンポーネント(部品、成分、構成要素等)を示しつつ、全体像はあえて余白として残すことで、読者の属人的事情を乗り越えるのではないか。ようするに読者のみなさんの「考える力」を借りることで、それぞれの事情にフィットしたケースバイケースの読書法が生み出せるのです。
本とどう付き合うのか?
私たちは無意識でいると、本に限らず内容を無批判で受け入れてしまう。その状態を「他人の頭で考える」状態だとすれば、情報が読者を素通りしていくだけなのです。ですので「懐疑」の存在は読書に欠かすことができません。何らかの新たな「問い」を持つことで、私たちの頭を駆動させるのです。
自分の頭で考える読書 変化の時代に、道が拓かれる「本の読み方」 [ 荒木 博行 ]
力みすぎ読書をめぐる問題点を「病」として、典型的な五つを本書では紹介しています。
・完読の病
・コミットメントの病
・積読の病
・実践の病
・読書時間不足の病
「完読の病」の章では、せっかく興味をもって買った本を、最後まで読まなくてはと思うことは多々ありますが、数ページ読んで面白くない本は読むのをやめればいい。ただし、タイミングを間違えてしまった本は、そのまま本棚に戻すのではなく、せめて何が書かれている本なのかという概要だけ把握して付箋などしておくことで、また旬のタイミングになった時に無言のサインが送られてきます。読書を楽しむ目的がいつの間にか、無理して完読など目的と間違えてしまう問題にも言及しています。