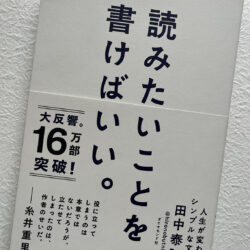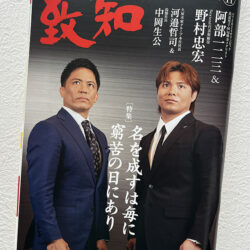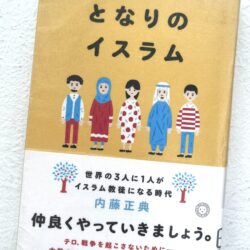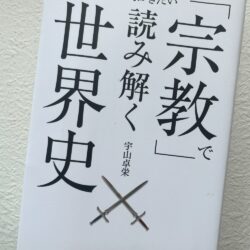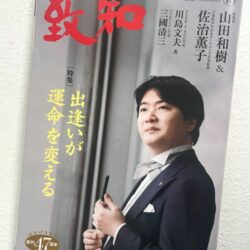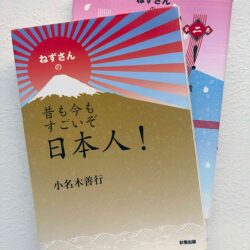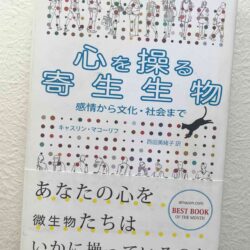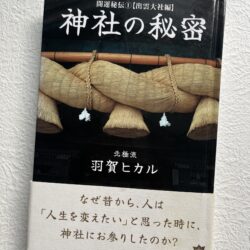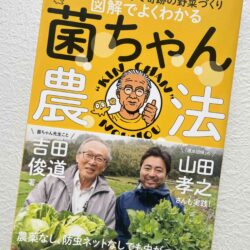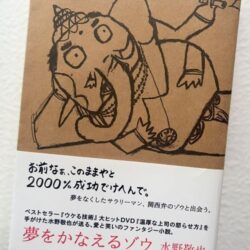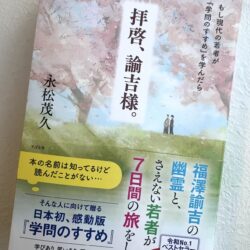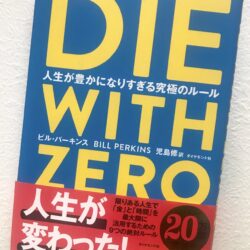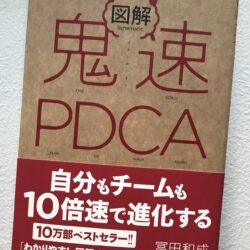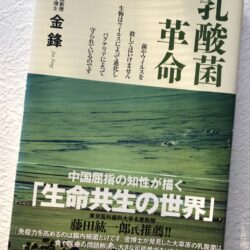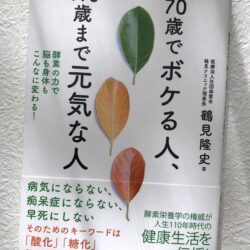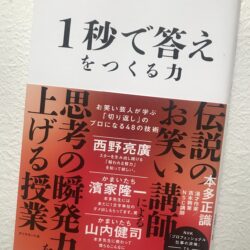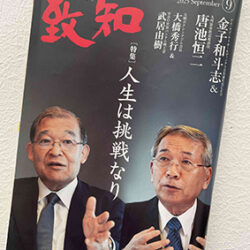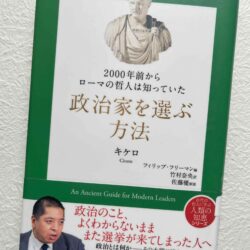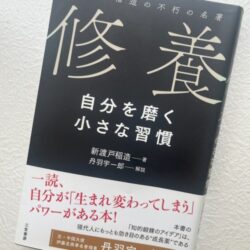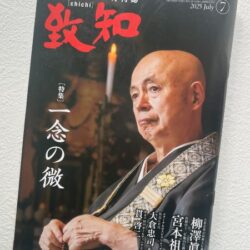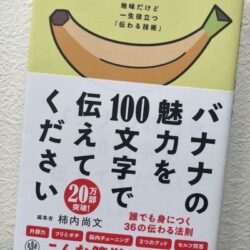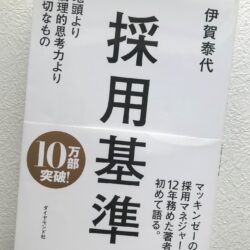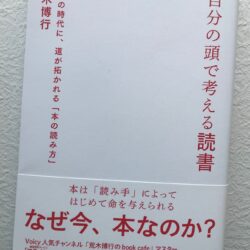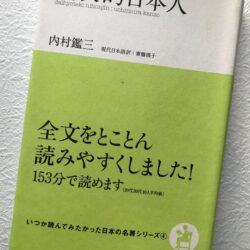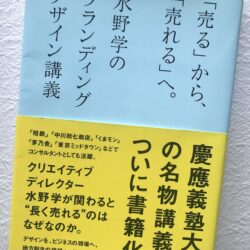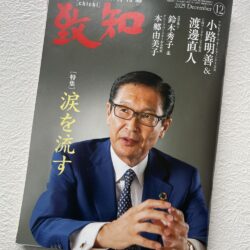 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 涙は人生に彩りを与えてくれる
釈迦の時代に生きた若い母親のゴータミー。産んだ赤ちゃんがすぐに死んでしまい悲しみにくれながら、「私の赤ちゃんを生き返らせる薬を下さい」と町中を歩き回った。気の毒に思った村人はお釈迦様なら薬をもっているかもしれないと教えた。
ゴータミーは森の中にいた釈迦を訪ね、生き返らせる薬を頼んだ。
「わかった。その薬をあげよう。しかしその薬を作るには白い芥子の種が必用だから、それをもらっておいで。ただし、その芥子の種は今まで一人も死者をだしていない家の芥子でなければだめですよ」
ゴータミーは急いで村へ帰り、家々を訪ねお願いした。どこの家も芥子をくれようとしたが、死者を出していない家は一軒もなかった。その時に彼女ははっと気が付いた。
世の中には大切な人と死にわかれていない人は一人もいない。
自分一人が不幸だと思っていたが、皆、大事な人と死別した悲しみに耐えて生きている。
お釈迦さまはそれを私に教えてくれたのだ。
自分だけが不幸だと、自棄になっている場合ではないのです。