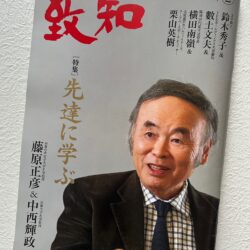 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 日本人の根っこには武士道と儒教、そして和歌があった
本誌は、まことに幸運なことに、多くの先達の言葉に導かれてきた。その中でも、特に心に刻まれている五人の言葉を紹介したい。いずれも時代も立場も異なるが、共通しているのは「人間はどう生きるべきか」という一点に、真剣に向き合っていることである。
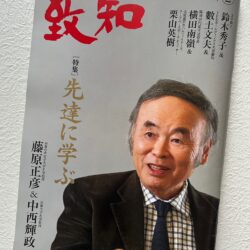 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 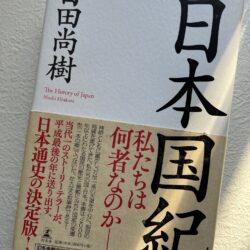 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 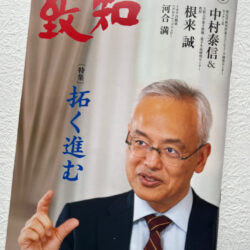 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 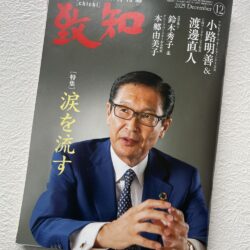 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 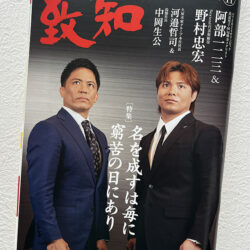 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 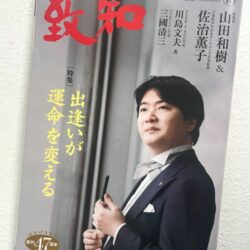 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 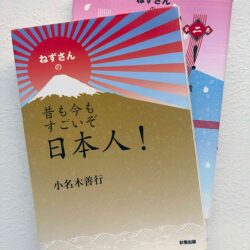 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 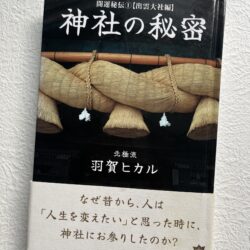 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 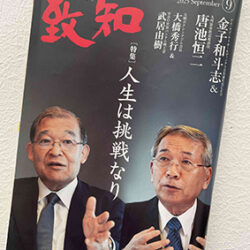 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本  歴史・哲学の本
歴史・哲学の本