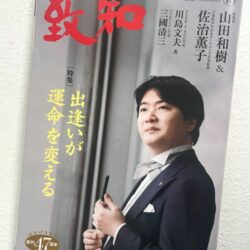 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 答えは内ではなく外にある
人間は一生のうち、逢うべき人には必ず逢える。しかも一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に
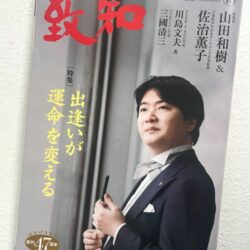 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 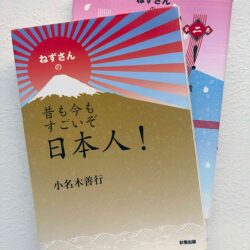 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 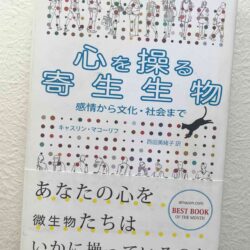 知識が広がる本
知識が広がる本 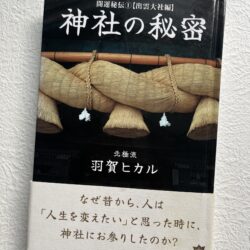 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本  知識が広がる本
知識が広がる本 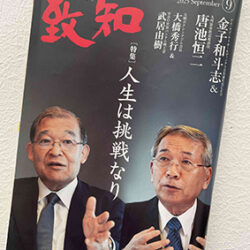 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 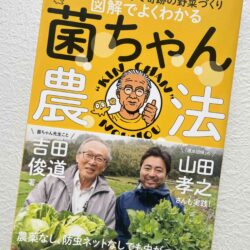 人生を楽しむ本
人生を楽しむ本  歴史・哲学の本
歴史・哲学の本 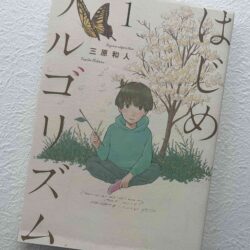 面白い方の本
面白い方の本 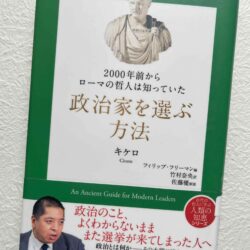 歴史・哲学の本
歴史・哲学の本