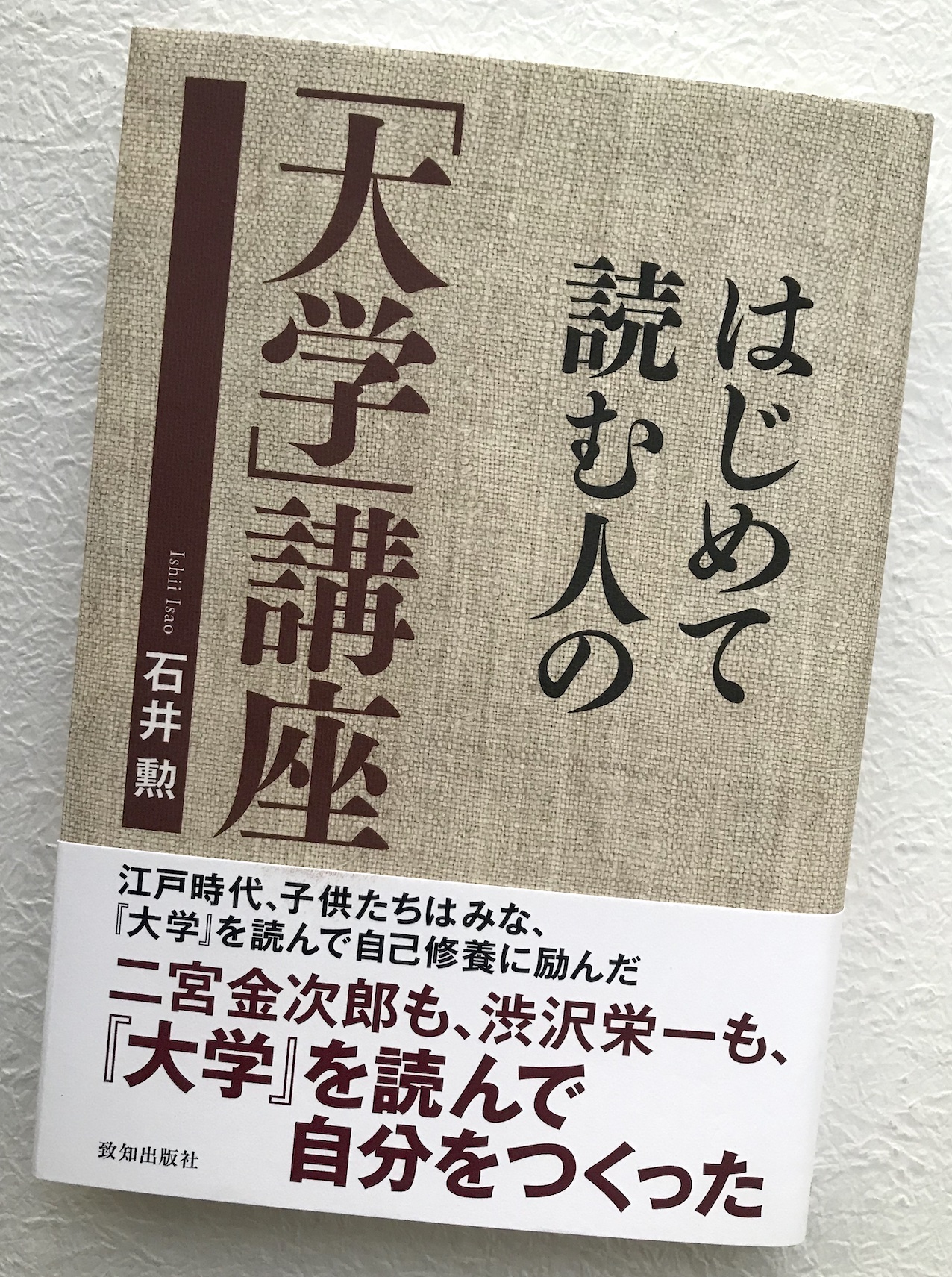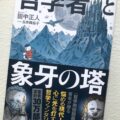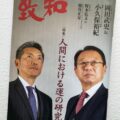「大学」「論語」「孟子」「中庸」、学問といえばまずこの四書で、明治の志士で読まない人間はいませんでした。この四書というのは人間をつくるのに非常に有意義な書物だったのです。この世の中をうまく運営し、国民を幸せにするために指揮を振るう。これが経世済民の中身ですが、それを実践するための必須学問が「大学」なのです。大学の道「明徳を明らかにするに在り。民を親にするに在り。至善に止まるに在り」は日本人の考え方の基礎となる本(もと)だと思います。
はじめて読む人の「大学」講座 [ 石井勲(教育学) ]
孔子の学問「四書五経」
儒教というのは、孔子を始祖といたしますが、その学問は孔子から曾子に伝わり、この曾子から孔子の孫の子思に伝わり、それから子思から孟子に受け継がれたと朱子は考えました。四書の一つ「論語」は孔子の言行を記したものです。孔子および孔子の門下の言行録です。そして、曾子の書いたものが「大学」であり、子思の書いたものが「中庸」(これには異論もあり)であり、孟子の言行録を書いたものが「孟子」です。この「論語」「大学」「孟子」「中庸」の四つの書物を朱子は四書と名付けました。個人の道徳や人格の形成に重点をおいています。
孔子の時代に「書」といえば、「歴史」のことでした。これを貴んで「書経」と呼ばれます。「書」と並んで「詩」も文章で残っていますが、これが「詩経」です。「経」は仏教でいうお経・経典という意味があり、尊い書物で「経」という字がつきました。「書経」は王家の歴史ですが、「春秋」は孔子の生まれた魯の国の歴史を書いています。それから孔子が晩年好んで熟読(韋編三度絶つ)といわれた哲学的な内容が多い占いの書、易に「経」をつけて「易経」。「礼」は礼儀作法や儀式についてまとめた書で「記」がつき、「礼記」となります。これが「易経」「書経」「詩経」「礼記」「春秋」の五つあるので、四書に対して五経といいます。政治、歴史、礼儀、文化の指針としての教えです。これらが孔子の学問です。孔子の学問を儒学と呼びます。儒教という言い方をしますが、学問としては儒学となります。
朱子学と陽明学
中国では孔子の学問が最も貴ばれました。宋代には朱子という大学者が現れ、一つ飛んで明の時代になると王陽明という学者が現れました。王陽明は、朱子の学問は昔の正しい姿が失われているといって朱子学を攻撃し、陽明学という学問を立てました。この朱子学と陽明学はともにわが国に入り、徳川時代の学問は朱子学が盛んになりました。しかし、陽明学や他のいろいろな流派も盛んになり、本家の中国に劣らないくらい立派になって、徳川から明治時代に受け継がれてきました。ところが明治以降、ヨーロッパ風の学問が起こり、学問がガラッと変わってしまったのです。
人生の大変な時期に良さがわかる
吉田松陰の伝記を読むと、「大学」はおそらく三歳ぐらいでやったものと思われます。昔の人は普通の人たちでも大体、三歳ぐらいから学問を始めたわけです。その頃の子どもは大人になって覚えるよりも楽に覚えてしまうのです。大人になると苦しんで覚える部分がありますが、わからなくても遊びの一つのようにやれるのです。これが人生で大変な時期、生きるか死ぬかという時に、良さがわかるのです。
<レビュー>
学習は楽しいもの
「勉強しなさい」と親はいう。「勉」は「力めて免れる」ということから、やらざるを得ず努力し、「強」は「しいる」こと。ですので勉強とは嫌なことを我慢してやるものなのです。それに対して学習はそうではない。学んで習うということから、この上ない喜びを感じさせるものなのです。学問とは元来、楽しいものなのです。教育こそ、日本をよくし、世界をよくする。「大学」でいう「其の本乱れて末治まる者は否ず」ということが1番の本(もと)になるんです。本が立たないから、末である国がちっともよくならない。子思は、まず「大学」を読んでから、次に「論語」、それから「孟子」、最後に「中庸」で結ぶのが一番いい順番といっています。二宮金次郎も薪を背負って読んだ「大学」を、ぜひ、皆さんも読んでみてほしいです。